足元に集中し過ぎて呼吸が荒くなった時には、焦らずにペースを落とす。途中で休憩を入れるのではなく、できるだけ一定のペースで淡々と歩き続ける方が、疲れを軽減してくれる。
あたりを見回すと、快晴の空に白い雲が幾重にも重なり、山の斜面と40度近い角度をつくっている。いつしか足元は急斜面の氷の壁となっており、踏み外したら命は無い。
ロープでお互いを結び合っているとは言え、誰か一人でも滑落したら、全員がその巻き添えになることは十分にあり得る。僕たちは声を掛け合いながら、ひとつひとつの動作に全神経を集中した。
そうやって数時間歩き続けて、やっと火口に到着した。火口近辺は若干斜度が緩くなるのでそれまでの緊張感が解れたが、そこには異様な風景が繰り広げられていた。
ぽっかりと口を開けた火口の周辺は、雪面が途切れて崖のように落ち込み、まるで蟻地獄のような不気味な様相を呈していた。火口内の数箇所からうっすらと立ちのぼる蒸気に混ざって硫黄の匂いがし、生贄の肉と骨を焼きつくす準備をしているように見えた。
僕たちはその周りを半周するかのように歩きつづけ、ついに一番高いポイントに到達した。
5450 メートルの制覇だ!
そこは火山岩が盛り上がった小さなスペースで、石ころ以外は何もない。何かを期待していた山登り初心者の僕にとっては、あまりに殺風景だった。いったい何を求めて僕はこの場所に辿り着いたのだろう・・・ そんな疑問が頭をかすめたが、富士山のように頂上にトイレや飲食店が完備(笑)されていなかったのが救いだった。
自分のこれからの一生の中でも、これ以上の高度に到達することはないだろう、ただその記録だけのために挑戦し達成したという、その満足感だけが頼りだった。
周りを見渡すと、雲がいくつもの層を成していて、すべてが自分の目線より下に見える。はるかかなたの雲海から突き出るように別の山が見え、僕の登頂を褒め称えてくれているように見えた。


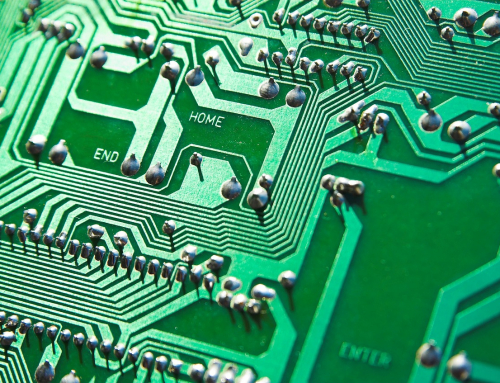





Leave A Comment