仮装パーティーの晩でなくとも、そういった仕草に本能的に長けた女の子もいる。ブロンドで派手な顔立ちをしたシェリーもそんなひとりだった。
ブロンドと言ってもさまざまで、貴金属のような重い輝きを放つブロンドや、太陽に光り輝くような明るい色のものまである。シェリーのブロンドは、両者の高貴な美しさを併せ持ったような明るい色の滑らかな髪で、大学の女子学生の中でもひときわ目立った。
多分そのせいだろう、彼女は男子学生たちの間で非常に人気があった。そして僕に対しては、初めて会ったときから不自然なほどフレンドリーだったのが妙に気になった。遠くから突然僕に声をかけてみては、どぎまぎする僕の反応を確認しながら微笑み返し、そのまま近くの男子学生と冗談混じりの会話を続けるのが彼女の常套手段だった。
シェリー: Hey Suchan! It’s been a while, isn’t it?
僕: Hi Sherry….. I haven’t seen you since last month….. Were you on a trip or something?
シェリー: Well, I’ve been around lots of places, you know. Oh Steve! What’s up?…
いつもこんな具合だ。同じクラスになったこともなく、カフェテリアで時々会話をかわす程度の間柄なので、特に共通の話題もない。僕に積極的に声をかけてくるのは、人脈の広さをアピールすることで自分の人気度を高めるための、一種の戦略だったのかも知れない。
こちらから話しかけた時は、満面の笑顔とオーバーなリアクションでしばらく楽しげに会話の相手をしてくれる。それでも、彼女の表情には何かを企んでいるような含み笑いが隠されている気がして、どうにも掴み所がない印象がいつも残った。
母国語でも男女の駆け引きは難しい。それが英語となると、通常の会話なら全く問題なくこなせても、スラングや慣用句の裏に潜むニュアンスまで理解するには、僕にはまだまだ経験が足りなかった。教室での発言や一対一の意思疎通においては、自分の英語力はネイティブレベルに達していたと自負していたが、男女が入り交じったグループ会話では苦労することが多く、その中に飛び込んでいくことが、なかなかできないでいた。
そんな僕に、まるで救世主とも思えるような友人が現れた。キャンパス中のあらゆるグループとの人脈を持ち、これには気をつけろ、あいつはこんなところがある、こんな集まりがあるから来ないかなど、僕にさまざまなアドバイスをくれた。


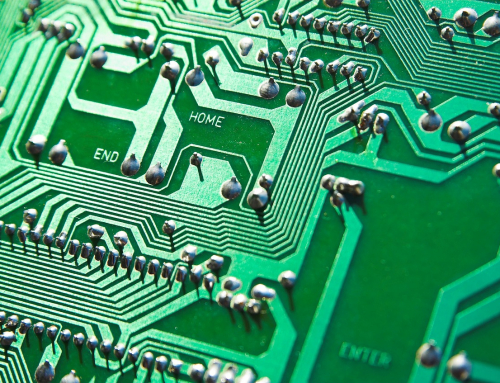





Leave A Comment