その数週間後に開かれたハロウィーン・パーティーでは、学生の奇抜で派手な衣装に僕は度肝を抜かれた。
今でこそ日本でもハロウィーンが一般化し、東京の渋谷などでは大量に繰り出した若者たちのマナーの悪さや、危険なレベルにまで達した人混みなどが問題になっているが、当時の日本では、公の場を仮装して歩くなど、外国人以外は考えられなかった。
ところが本場は流石に違う。大学のメインホールを明け渡したパーティー会場で、学生たちは自らのオリジナリティを、ここぞとばかりに発揮していた。
ドラキュラに扮したヤク中の男子学生、猫とバニーガールを足したような服装の女の子、映画「時計仕掛けのオレンジ」の主人公そっくりの衣装と化粧を念入りにほどこした友人、全裸に近い服装で全身に絵の具をペイントして現れたカップル、1950年代のロックンローラーの服装で男女を逆に変装しているカップルなどなど・・・
僕はと言えば、面白いアイデアも衣装も思いつかず、悩んだ末に浴衣と(なぜか)扇子で参戦した。案の定、そんな民族衣装もどきはワイルドさに欠け、まったくもって相手にされなかった。結局、どこからともなく現れた神秘的な少女、シンディーに心惹かれ、声をかけた。魔女に扮しマントに身を包んだ彼女から、その衣装がベッドカバーだということを聞いて驚いた。
この晩のシンディーもそうだったが、仮装は人を変える。特に女の子の場合、仮面をかぶっているという安心感なのか、おそらく無意識ながらも、妙に不思議な行動に出るのだ。それは時に、僕たちを禁断の園に踏み込ませようとする。
僕はシンディーの扮する魔女の雰囲気に半分酔いしれ、その妖しい魅力と会話の虜になり、絶対に彼女にしてみせよう、などと勝手に思い込んでしまっていたのだ。(ところが翌朝、すっぴんの顔で妙にサバサバしたシンディーにカフェテリアで会った時、僕の恋心は吹っ飛んでしまった。正直、ちょっと残念だったが、これが現実というものだろう・・・)
始まった頃は「仮装大会」的な雰囲気だったハロウィーン・パーティーも、深夜の零時を回るころから、皆、思い思いに楽しむようになる。着ていた衣装を脱ぎ捨てて普段着に着替え、キャンパスの芝生で大騒ぎを続ける者や、ホールでダンスを楽しむ者、グループごとに随所で継続されるパーティーに参加する者などさまざまだ。
一晩中、キャンパスには狼のような声がこだまし、暗闇からは今にも妖怪が飛び出して来そうな気配が漂う。
住宅の玄関に飾られたパンプキンの目からは、ゆらゆらとロウソクの光が漏れ、侵入者を威嚇しているようにも見える。どこに行ってもハロウィーンの魔力から逃れることはできず、朝になって太陽光が邪気を洗い流してくれるまで、悪魔のマジックは続く・・・
深夜2時過ぎ。
どこに行こうかと、ビールを飲みながらホールでぼんやりダンスを眺めていた僕は、近くに立っていたロリーを見つけ、声をかけた。彼女のことは以前から知っていた。長身でプロポーション抜群の彼女は、いつもセクシーな雰囲気を全身から漂わせており、大学の中でも非常に目立つ存在だった。
この晩の彼女は、突然話しかけた僕に親しげな笑顔で答えてくれ、まるで僕を誘っているかのような妙に親密な会話を続けた。やがてどちらから誘ったということもなく、僕たちは一緒に踊り始めた。彼女の視線や身体の動きが、僕を虜にしたのは言うまでもない。
結局、僕は朝まで、彼女とつかず離れずの奇妙なダンスを踊り続ける羽目になった。


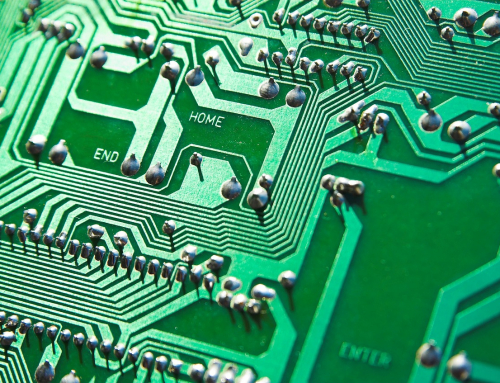





Leave A Comment