ヤバイ! 直感的にそう感じた。
安全のためにリフトが止まることはよくある。でもこれは何かが違う。改めて前方をよく見ると、先の方まで誰一人乗っていない。後ろを振り返っても同じだ。慌てて飛び乗ったので気に留めなかったが、思い返せばリフト乗り場は灯りが消え、小屋の入り口も閉まっていた・・・ そうだ、夕闇が迫る前にとっくに営業を終了していて、何らかの理由で空運転していただけなのだ。僕はそれに飛び乗ってしまった!
不安がつのる中、僕はリフトが動き出すのを待った。10分、20分・・・
いくら待っても、動き出す気配は無い。あたりは闇と静寂が深まりつつある。試しに大声で叫んでみた。し~んと静まりかえった斜面や樹木の間からは、何ひとつ反応はない。二度、三度と、声の限りをつくして叫んでみても、静寂の中に吸い込まれていくだけだ。
そうだ、ストックでリフトを叩こう! 誰かが音を聞きつけて、事態に気づいてくれるかも知れない。ガン・ガン・ガン、ガ~ン・ガ〜ン・ガ〜ン、ガン・ガン・ガンと、僕はリフトの支柱やフレームを、ありったけの力で叩き続けた。途中からはモールス符号のSOSに切り換えた。が・・・何も起こらない。
状況は明らかだった。リフト乗り場にも、終点にも、山の斜面にも、もう誰もいないのだ。斜め下のスロープは既に暗く、もちろん照明もない。こんな時間に滑り下りるスキーヤーなど、いるわけがない。
そうやって1時間が経過した。日がとっぷりと暮れた冬山は、さすがに冷えてきた。
こうして寒さに耐えながら、このまま救助を待つしかないのか・・・ 問題は、助けがいつ来るかだ。アメリカのスキー場で、そもそもパトロールなんて習慣があるのかも分からない。日本とは比べものにならないくらい広いこのスキー場で、救助隊が僕を発見してくれる確率は相当低いだろう。
戻って来ない僕を案じて、デニスが警察に通報してくれるかも知れない。でも能天気なデニスのことだ。深夜ぐらいまで、いや朝になるまで待たないと、何もアクションを起こさないことは十分に考えられる。当てにならない救助に望みを託して、寒さと戦うなんてまっぴらゴメンだ。ましてやリフトの上で凍死なんて、見せ物みたいでカッコ悪すぎる。自力で状況を打開する方法はないか・・・ 僕は必死で考えた。
下を見ると、雪が積もった斜面までは10メートルはありそうだ。飛び降りるなんてあり得ない。
リフトのロープまでよじ登り、ロープづたいに地面との距離が近いところまで移動できないか・・・ これも無理だ。前を見ても後ろをみても、地上との距離は縮まるどころかより高くなっている。終点まで登り切るには体力がもたない。ロープを掴んで始点まで滑り下りるのは危険すぎる。ロープを握りながら何とかひとつ下のリフトまで行っても、そこで停止できる保証はない。誤って落下したら、今よりももっと危険な場所に落ちることだってあり得る。
前も駄目、後ろも駄目となると、残された道は下しかない。僕は、真下の雪の斜面をもう一度見た。
こんな高さから飛び降りた経験はない。着地と同時に回転してショックを和らげるには、斜度が足りない。リフトの下にぶら下がって手をいっぱいに伸ばしてもせいぜい2メートルだ。足先から地面まではまだ8メートルもある。足元の雪はおそらく10センチぐらいの深さで、多少はクッションの役割をしてくれるだろう。でも着地のショックで骨折でもしたら大変だ。自力で山を登って、反対側のふもとまで滑り下りるのは不可能となる。
あれこれ考えながら、僕は半ば決心していた。
飛び降りるしかない。飛び降りた際の衝撃を極力和らげ、怪我のリスクを最小限に抑えるにはどうすればいいのか・・・? スキーは外そう。僕はビンディングを緩め、愛しのK2を片足ずつ放り投げた。スキーが雪面に埋まる様子で、雪の状態と深さがわかる。新雪が寒さで凍った少し硬めの雪のようで、緩衝材の役目は果たしてくれそうだ。
さあ、ブーツはどうするか。今のまま固くバックルを締めたままだと、着地の際にブーツの上の部分で骨折するかも知れない。そうなったら歩くことはおろか、激痛にもがき苦しむことになるだろう。バックルを緩めるとどうか。足首が自由になるので、捻挫程度で済むのではないか。ブーツの中で足が動き、多少ショックが和らぐ可能性もある。いっそブーツも脱ぎ捨て、素足で着地したらどうなるか。着地の衝撃が、何の保護もない素足に直に伝わるだろう。交通事故の際に、道路に放り出されるみたいなものだ。やめておいた方がいい。
着地の状況を想像しながら、僕は頭の中で何度もシミュレーションした。
方針は決まった。バックルを緩め、ブーツを穿いたまま飛び降りるのだ。そう決心した僕は、片足ずつブーツのバックルを外していった。強く締めていた足首から足先まで、血が巡っていくのが分かる。
さあ、やるぞ。
もう一度、はるか下に見える雪面を注視した。あの雪の吹きだまりに着地するのだ。膝を柔らかく使ってショックを吸収し、尻、そして腰から上を柔軟に衝撃に合わせるのだ・・・
もう迷いはない。僕はリフトのクッションに預けていた体重を、支柱の両手に移した。そこから徐々に下に持ち替え、チェアの一番下のフレームを両手でしっかりと握った。さあ、ここからだ。しっかりと握っている手の感触を頼りに、僕は全身を空中に投げ出した。
まずは成功だ。僕の全身は、リフトの真下にぶら下がるように、しっかりと伸びきった。もう後戻りはできない。僕は両腕をいっぱいに伸ばし、膝に神経を集中しながら、固く握っていたリフトのフレームを手放した。
ドサッ・・・ 鈍い音がして、僕の両足のブーツは、半分斜めになりながら雪面に突き刺さった。半分尻もちをついたが、思ったより深かった雪が、衝撃を吸収してくれていた。背骨に損傷はない。ブーツの中では、僕の両足が動いている。痛みはない。助かった!
僕はしばしその場で、神に感謝した。
あとは宿に帰るだけだ。僕はスキーを担いで斜面を登った。周りの雪明かりが、僕の決断を祝福しているようにも見える。清々しい気分だった。


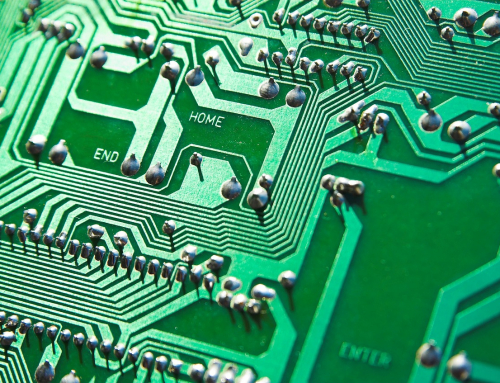





Leave A Comment