翌朝、ひとりがチェックアウトの手続きをしている間に、僕たちは音を立てないようにひとりずつ部屋から抜け出した。不運なことに、僕は最後の退出者だった。フロントデスクの横を何食わぬ顔でゆっくりと通り過ぎようとする僕の斜め後ろから、疑いの視線を感じた。
続いて僕を呼び止めるような声がしたが、僕は反射的に歩調を速めた。そしてそれがいつの間にか全力疾走に変わり、大声で叫びながら追いかけてくるホテルの従業員を振り切るようにして、僕は待ち受ける車に飛び込んだ。ぎりぎりセーフだ。急発進する車の中で、皆が拍手喝采で僕を迎えてくれた。
あとは、ひたすら家路だ。行き同様のむさ苦しい車中泊で60時間のロング・ドライブだが、登頂の達成感のおかげか、清々しい気分だった。
途中でクルマのトラブルがあったが、今回のワンボックスカーを提供してくれたジョンはクルマのメカに詳しい。僕たちは住宅街の庭先で丸一日待機することになったが、近くのパーツ屋までヒッチハイクで行って部品を調達してきたジョンは、まるで当たり前のようにテキパキと修理してしまった。日常の足としてクルマが不可欠なアメリカでは、たいていの男性はクルマのメカに通じていて、少しぐらいの故障なら自分で修理してしまう。ガソリンスタンドやディーラーに頼り切っている日本のカーオーナーたちとは雲泥の差だ。
ハンバーガーとホテル泊の贅沢に味をしめたせいか、狭い車内での連泊に絶えられないという意見もあり、ある晩、僕たちは南部の見晴らしのいい駐車場に車を停めて、寝袋で車外泊をすることにした。欧米では、こうした無防備な状況に自らを置くことは希だが、襲われるリスクと状況・対応策を十分に認識した上での判断だ。
狭い車内泊から一転して、開放的な空間で寝袋にくるまり温かい眠りに落ちた僕は、夜中にふと目を覚ました。
夢、それとも現実?・・・ そこには信じられないような光景が広がっていた。これまで見たことの無いような満天の星空が頭上に広がり、まるで紺碧の夜空をほうきで掃くかのように、無数の流れ星がつぎつぎと現れては消えた。その晩は流星群が地球の近くを通過したのだろうか、これほど多くの流れ星を一度に目撃するなど、おそらくもう一生あり得ないだろう。
登山ツアーは相当な冒険だったが、生き抜くことの素晴らしさを体験できた。 大半が登山初心者であったにも関わらず、誰一人病気にもかからず怪我もなかったのは、リーダーのダグに荒野で生き抜くアメリカン・インディアンの感性が備わっていたからだろうと思う。


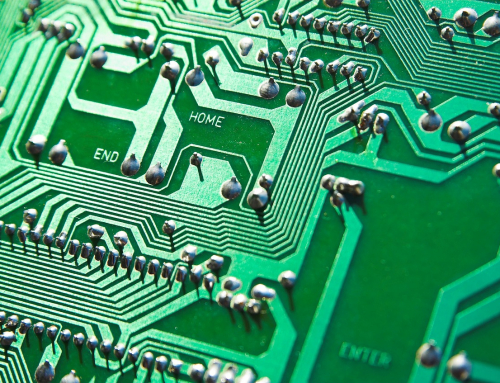





Leave A Comment