最初は、トイレも、シャワーも、マットレスも、まともな食事も無い毎日が途方も無く心細く思えたが、不思議なことに、3日目ぐらいからは慣れるものだ。お洒落や美食は都会にいるから必要なのであって、生きていく分には全く関係ない。最も大切なことは自分の体調管理で、十分な水分をとり身体の異変に敏感に対処していくことが自己責任として課せられた。
大自然の中で、自分の装備以外は何も頼ることができないというのは独特の緊張感があり、感覚が研ぎ澄まされていくような気がした。
人参が大嫌いだった僕は、さすがに野菜がそれしかないということで、ポリポリと丸ごとかじることができるようになった。大豆が原料の乾燥肉もどきも、肉だと思い込んで食べれば結構うまい。木の葉をトイレットペーパーの代わりに使用するのもなかなか衛生的だと思えるようになった。
ピーナッツとクッキーと干しぶどうを混ぜて袋に入れた gorp と呼ばれる栄養補給食をランチの代わりにするのだが、塩と甘味が混ざり合ったその奇妙な味に、最初はとても馴染めなかった。ところが、歩き回って体力を消耗し身体がエネルギー補給を要求してくると、そんな gorp ランチでもひどく待ち遠しくなるのだ。
ハイキング三日目の朝、スコットが体調の異変を訴えた。吐き気が止まらず、朝食後しばらくすると、嘔吐を繰り返すようになった。
僕たちはリーダーのダグを囲んで、横になったスコットに目を配りながら対応策を話し合った。
やがてダグが出した結論は、スコットをひとりキャンプに置いて、通常通りハイキングのトレーニングに出かけるということだった。下山して手当を受ける必要が出てきても、キャンプならばそのままクルマに乗せて麓の医者に連れていける。まずは動かさないで休養をとらせ、半日ぐらいは様子を見るべきだとの判断だ。
ハイキングの予定をキャンセルして全員がキャンプに残ることも検討したが、貴重な一日を無駄にすることはかなりの犠牲を払うこととなる。高度順応が不十分なままで山頂にアタックするのは疲労や高山病のリスクが大きくなる上、山頂アタックがギリギリのタイミングになればなるほど、判断や行動に焦りも出てくる。
スコットの看病に1名だけ残るという選択肢もあったが、病状はそこまで悪くないようだった。当日は少し早めに午後の予定を切り上げることにして、僕たちはスコットをひとり残してキャンプを出発した。
誰もがダグの経験と感性を全面的に信頼し、その指示に率直に従うという、理想的なチームワークが保たれていた。


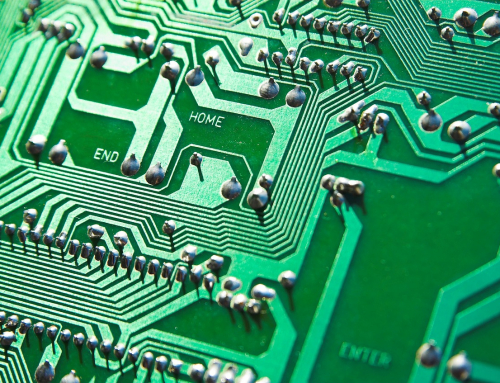





Leave A Comment