やがて、母がその先生に呼び出された。このままの髪型を続ける限り、志望校への推薦状を書かないという。
僕は国立大志望だった。留学は公費であったものの、ホストファミリーに対するお礼などで父に経済的負担もかけたし、できるだけ安く早く大学を卒業して、経済的に自立したかった。ただし、行くならば東京の大学と決めていた。2年前に姉が上京していろいろ情報が入ってきていた。東京には何かがある、僕は漠然とそう考えていた。
工学系が自分の強みだと思っていたので、東工大と東大にターゲットを絞った。(目標はデカイ方がいい!) ただし東大は総合的な学力が必要なので、多分無理だろうと感じていた。
母は、担任の先生の言い分を全く相手にしなかった。僕の髪型と推薦状の重要性を母親として判断した結果、僕の髪型を優先してくれたということだ。いや、優先してくれたのは僕の髪型ではなく、僕の意思だ。実際、母は僕の長目の髪型には否定的で常に切れといっていたが、母が真っ向から反抗したのは、古い基準で物事を決め付けるその先生の思考回路だった。僕に対しては何も言わなかったのが母の凄いところだ。
9人姉妹の末っ子として知多半島の暖かい海辺で生まれ、毎日新鮮な魚介類を食べながら、笑いの絶えない家庭に育った母は、陽性でおおらかな性格とチャキチャキとしたおてんば娘の両面を併せ持っていた。幼い頃からアメリカ映画に親しみ、マッカーサーのような外人男性に憧れ、外人と結婚することを半ば決めていたようだった。
一方、父は15代伝わる山奥の伝統的な家系に生まれながらも、両親を早くして亡くし、戦後の農地改革で全てを失い、先祖の栄華の記憶と遺産を頼りに昭和中期を生き抜いてきたせいか、人付き合いは苦手だった。
こんな水と油のような父と母が結婚したのは、父が、まず自分の弟を偵察隊として知多半島まで送り込み、後に自らが乗り込み、まるでイングリッド・バーグマンのような母の美貌に一目ぼれし、「上の娘ならば準備ができている」と言う先方の両親の言葉を突っぱね、ほとんど無理やりに見合い結婚を成就させたからだ。
母は、数年以内に田舎町から都会に引越すことを条件に父と結婚し、嫁ぎ先の伝統的家系の古いしきたりに耐えながら、姉と僕を産んだ。
常に新しいものを理解・吸収し続ける母のDNAと、先祖を敬い伝統文化が創り出した芸術を愛する父のDNAの両方が、今でも姉と僕の中に生き続けている。


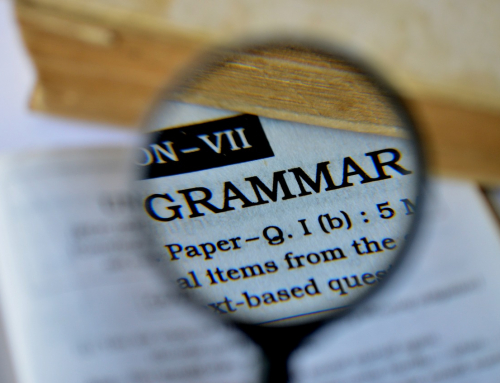





Leave A Comment