当初はビクビク・ドキドキの連続だった僕も、日本人の得意科目である数学のおかげで不良生徒にも一目置かれるようになり、市民権を得たような気分になった。
数学は圧倒的に日本が進んでいた。アメリカの高校では Linear Algebra(線形代数)の基本に触れるのみで、行列演算や配列、微分積分などは大学でしか学ばない。もともと何の役に立つかわからない科目だけに、大半の生徒は学ぶ意志を完全に放棄しており、理解の域を超えたテストで毎回満点をとる僕を、不思議そうに眺めていた。
American Government(アメリカ政治)は、ベースとなる知識が全く無い僕にとっては超難関だった。もともと社会科が大の苦手だった僕にとって、今さら苦労してアメリカ政治を覚えても何のメリットもないが、陽気な担任の先生の専門分野だったこともあり、多少は勉強した。
驚いたのは、filibuster(議事妨害)という不可思議な戦略についてその正当性が当然のように説かれた点で、変な国だなぁと思ったことが記憶に残っている。担任の先生はアマチュア無線部のアドバイザーでもあり、僕のホストブラザーとも気が合ったので、よく話しをした。
英語(つまり国語)の授業は超美人の先生だった。椅子が固定された小さな机を先生の周りに並べ、毎回いろいろな作品について意見交換が行われる。和気藹々とした雰囲気を期待していたが、美人先生は生徒にからかわれないよう、意図的に奇怪な言動を心がけているように見えた。
不良だらけの教室では、女の先生は決して笑顔を見せてはいけない。生徒に優しく接した途端「甘い先生」とのレッテルが貼られ、ワガママと悪戯の総攻撃を食らうことになる。
威厳を保つためだろうか、その先生は、シェークスピアの古典を重点的に教えた。現代英語をまずマスターしたかった僕にとっては全くの無駄で、毎日、宿題のペーパーバックを読み始めると、10分もしないうちに睡魔が襲ってきた。例えば your を thy と言う古典文学は、単語も文法も現代英語とは大きく異なり、日常生活では全く役に立たない。まるで日本に来たばかりの外人に漢文を教えるようなものだと思った。
アメリカではスピーチの教科が義務づけられており、生徒は「正しい英語」で話す練習を積む。日本の中学・高校で英文法を学ぶ日本人高校生にとっては当たり前のような内容ばかりだが、それを口に出して皆に伝えるという点では、非常にためになる科目だ。立つ位置や動き、ボディ・ランゲージなどもカバーしている点には驚いた。
タイピングのコースは非常に有益だった。当時はもちろん機械式のタイプライターで、電動タイプライターすらまだ普及していない。両手を常にホームポジションに置き、キーの位置を指に覚え込ませてブラインドタイピングができるようにするのは当たり前だが、どの指で打った文字でも均等に印字されるよう、練習を繰り返す。
例えば A とか Q は、左手の小指でタイピングするので弱々しい印字になることがあるが、それを右手の人差し指でタイピングする J や M などと同じ強さで打てるのが理想だ。ちょっと年増のオバちゃんのような先生が、最初は掛け声をかけながら皆で同じ文字のタイピングを繰り返す。やがて紙に書いた原稿を見ながら各自がタイピングし、でき上がったものに印字のムラがないかをチェックしてもらう。
僕はこのタイピング・クラスが大好きになり、クリスマス・プレゼントとしてタイプライターを買ってくれるよう、ホストファミリーにねだった。
タイピングやスピーチなどの実践的なクラスを除いては、どの教室でも先生を困らせて友人たちのウケを狙う言動が目立った。机を並べてひたすらノートをとる日本の進学校とは、まったく異なる授業風景だった。




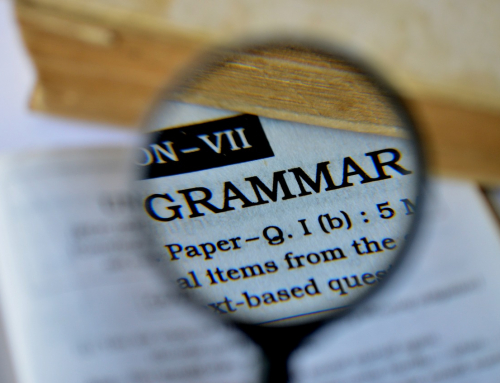



Leave A Comment